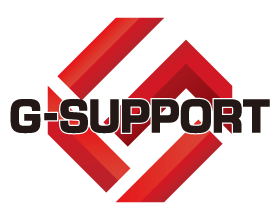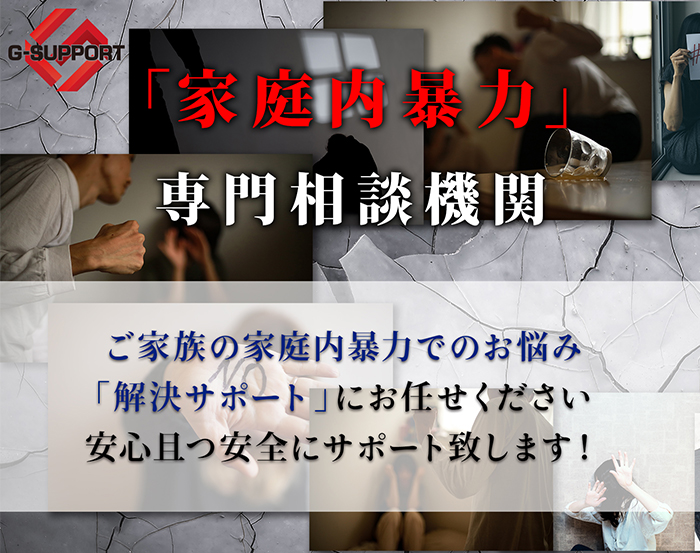ニュース情報
日本で「うつ病の子供」が急増している根本原因
2019.09.29
さまざまな原因から「生きづらさ」を感じる人が増えている。摂食障害、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、依存症、原因不明の身体の痛み……。精神科医の岡田尊司氏は、「そうした症状の背景には、幼少期に家庭できちんとした愛情を受けられなかったことが影響している恐れがある」という――。
※本稿は、岡田尊司『死に至る病』(光文社新書)の一部を再編集したものです。
※本文中の事例は、具体的なケースをヒントに再構成したものであり、特定のケースとは無関係です。
■家庭のいざこざがうつのきっかけに
本来、うつ病は中高年の病であった。そして、子どもには非常に稀(まれ)なものとされていた。子どものうつに関する論文を調べても、戦前にはほとんど見当たらず、アメリカの専門医学雑誌に、ようやく一本だけ見つけ出せたが、そこに報告されていた八歳の少女のケースには、どこか現代に通じるようなシチュエーションが認められる。少女は一人っ子で、両親から、とりわけ父親から可愛(かわい)がられて育った。過保護といってもいい環境だったといえる。経済的にも裕福で、何不自由なく暮らしていた。ところが、大恐慌の影響で、父親の収入が大きく減ってしまう。しかし、贅沢(ぜいたく)に慣れた母親は出費を減らすことができず、父親はそのことを不満に思っていた。そんな悩みを相談しているうちに、父親は別の女性と懇ろになり、一線を越えた関係になってしまう。 そのことを知った母親は、非常にショックを受け、両親の間では修羅場が繰り広げられることになった。少女は、母親を裏切った父親と、半狂乱になった母親が争う場面を目にすることになったのだ。
少女は、ふさぎ込み、学校にも行かなくなってしまう。学校に行ったときには、教師がいれば、教室に入ることもできたが、教師の姿がなくなると、教室にいられなかった。その症状には、父親が家からいなくなってしまうのではないかという不安が影響していたと考えられた。
■1990年代から増え始めた子どもの躁うつ病
この少女のケースのように、子どものうつは、家庭環境、とりわけ両親の仲が影響しやすい。ただ、この論文の著者も述べているように、子どもがそのストレスを「うつ」という形で表現することは稀で、身体的な症状や、行動上の問題(たとえば万引きや抜毛といった行動)で表すことの方が多い。
実際、戦後の1950年代においても、子どものうつに関する論文はごくわずかであった。ところが、1960年代くらいから徐々に増え始め、その後は指数関数的な増加を認めている。
双極性障害(躁うつ病)は、成人、中でも壮年期に発症することが多く、子どもでは極めて稀か、存在しないとさえいわれていた。
1950年代には、子どもの双極性障害のケースが報告されているが、極めて稀で、一年間に一本も論文が出ていない年もあった。60年代、70年代と、症例報告が少数ながらされていたが、その頻度は依然少なく、1979年に、その道の専門家が「稀に存在することは否定しないが、私自身は、まだ一例も子どもの躁うつ病をみたことがない」と述べているほどであった。
しかし、その後、報告は徐々に増え始める。1990年代には、それほど稀なものではないと考えられるようになるとともに、ADHDと併存しやすいことに注目が集まるようになった。
2000年に出た論文では、子どもの躁うつ病が、大人の躁うつ病とは異なり、ADHDや攻撃的行動、非行、薬物乱用などを伴いやすく、また、虐待や不遇な環境との関連が強いことを指摘している。
■子どものうつ病はある時期爆発的に増えた
そして、異常ともいえる増加が起きたのは、1990年代後半以降のことである。
1994年から1995年までと、2002年と2003年までの間に、外来で診療を受けた患者数を比べると、10代までの双極性障害は、約40倍にも増えていたのである。有病率にして、人口比で約1%に達した。
それに対して、20代以降の双極性障害の外来患者数は、約1.8倍に増えたに過ぎなかった(人口比で約1.7%)。
もちろん、認知が進んだということもあるだろうが、かつては存在しないとまでいわれ、わずか20年前には専門家さえも1例もみたことがないとされた子どもの双極性障害が、ごくありふれた疾患となったのだ。
1%の有病率というと、たいした頻度ではないと思われるかもしれないが、これは、双極性障害の中でもⅠ型と呼ばれる激しい躁状態を呈するタイプだけの頻度であり、大うつと軽躁を繰り返す双極性Ⅱ型などの、もう少しマイルドなタイプも加えた子どもの双極性障害の有病率は、実に7%にも達すると報告されている(2009年)。
このように、この数十年の間に、過去の常識を覆すような事態が次々と起きているのである。
■「ADHD」の定義があいまいになってきた
そして、子どもの双極性障害と縁が深いとされたADHDの爆発的な増加も、「現代の奇病」の一つといえるだろう。
ADHD(注意欠如/多動性障害)は、神経発達障害の一つで、遺伝要因が7~8割と推測され、先天的な要因が非常に強いとされてきた。遺伝性の強い疾患であれば、大昔から存在したはずであり、数十年の間に急増するということも、通常は考えにくい。ところが、あり得ないはずの奇妙なことが起きているのである。
ADHDの歴史を調べたマシュー・スミスによれば、いくら時代を遡(さかのぼ)って文献を渉猟しても、ADHDらしき人物の描写や記録はほとんど見つけ出すことができないという。大昔から存在する遺伝性の障害であれば、それらしき例がシェークスピアやモリエールの戯曲の登場人物として、あるいは、医学的な文献に見つかりそうなものだが、一向に見当たらないのだ。今日、知られているもっとも古いADHDの症例だとされているのが、1902年にイギリスの小児科医ジョージ・フレデリック・スティルが報告したもので、そこには、多動や衝動性を特徴とする20のケースが記載されていた。 ただ、それらのケースは、多動や衝動性のほか、破壊的暴力行為や自傷、道徳的な抑制欠如などを呈し、ADHDというよりも、情緒障害とか破壊性行動障害として理解されるべきものであった。しかも、その多くは施設に収容された子どもで、今日では、愛着障害だと診断される可能性が高い。遺伝性が強いとされるADHDと同じものだとは、とうてい言えそうもない。
つまり、ADHDは、その起源においてさえ、すでに危なっかしい混乱の兆候がみられるのである。
■多動や衝動性、不注意があってもADHDとは限らない
多動や衝動性を呈する子どもに再び関心が注がれたのは、1920、30年代のことである。当時、ウイルス性脳炎がアメリカで猛威をふるい、多くの子どもたちがその犠牲となった。一命を取り留めたものの後遺症に苦しみ、無反応に何年も眠り続けることもあれば、多動や衝動性、不注意、知能低下、麻痺、けいれん発作などを来たす子どももいた。
そんな子どもたちを収容していた病院で、偶然、覚醒剤アンフェタミンが不注意や多動に効果があることが発見された。
確かに、多動や衝動性、不注意といった症状が認められはするが、これらは、脳炎後遺症による脳の器質的障害によるものであり、遺伝性が強いとされるADHDとは、似て非なるものであることは明らかだ。
それからしばらくは、子どもたちの多動や不注意になど、ほとんど関心が払われることはなかった。
■1950~60年代に突如目立ち始めた「小児期の多動」
今日のADHDに相当するとされる診断が登場したのは、1957年のことである。児童精神科医のモーリス・ラウファーとエリック・デンフォッフが「多動・衝動性障害」という診断概念を提案したのだ。
この診断概念が、わずか5年後、「小児期の多動反応」として、正式の診断基準に採用されると、「多動」は、たちまち市民権を得る。というのも、ちょうどこの頃、学校では、落ち着きがなく、授業に集中できない子どもたちが問題視されるようになっていたからだ。
つまり、今日のADHDらしき状態は、1950年代後半から60年代にかけて、アメリカにおいて突如目立つようになったということになる。
この頃、何が起きていたのか。
■ADHDの薬をもらうことが一般的になった
一つは、戦後のベビーブームで、教室が子どもたちであふれかえっていたという状況があった。
また、先述のマシュー・スミスによれば、アメリカの学校では、もう一つ異変が起きていたという。それは、ガガーリン少佐の「地球は青かった」と関係していた。史上初めての有人宇宙飛行にソ連が成功したことは、アメリカに強い衝撃を与え、科学教育にもっと力を注ぐべきだという機運が生まれた。それは国の威信をかけた強い圧力となって、教師や生徒たちにのしかかるようになったのだ。
算数や科学が重視されるようになり、授業についていくことができずによそ見ばかりしている子どもたちは、もはや大目にみられることはなく、医者に行って、薬をもらうようにと助言を受けるようになった。
折しも、1960年には、アンフェタミンよりも作用がマイルドで、依存しにくいとされるリタリン(一般名メチルフェニデート)が小児の多動症治療薬として発売された。リタリンは、その後、指数関数的に売り上げを伸ばしていくことになる。
とはいえ、それから27年後の1987年において、リタリンを服用としているのは、小児の0.6%に過ぎなかった。ところが、その10年後の1997年には、2.7%と4倍以上に膨らみ、2011年になると、ADHD薬を投与されている子の割合はおよそ6%に、ADHDだと診断された子の割合は約10%にも達している。
この事実を前に、改めて疑問に思う人は少なくないだろう。ADHDは、遺伝性の強い神経発達障害ではなかったのか。同じような先天的要因が強い神経発達障害である知的障害や学習障害では、この何十年か、有病率はほとんど変化していない。この違いは、何を意味するのか。本当のところ、一体何が起きているのか。
■戦後増え始めた子どもの症状は愛情不足が原因だった
「ADHD」のほか、「境界性パーソナリティ障害」「摂食障害」「子どもの気分障害」は、戦前には非常に稀なものだったのが、1960年代頃から徐々に増え始め、その後、爆発的な増加に至っている。
それは、単なる偶然の現象なのか。それとも、何か共通する要因がからんでいるのか。
実は、「境界性パーソナリティ障害」「摂食障害」「子どもの気分障害」「ADHD」は、不安定な愛着との関連が強いだけでなく、幼い頃に母親との間で不安定な愛着を示した子で、発症リスクが大きく高まることが裏付けられているものばかりである。
たとえば、摂食障害のケースで、典型的に認められる状況は、支配的で、過保護・過干渉な母親と、腰の引けた無関心な父親の間に育っているということだ。母親は子どものことを思っているつもりなのだが、実際には、自分の基準を子どもに押しつけている。共感的な関わりが苦手で、子どもに対して指導するか、非難するかという関わり方しかできないということが多い。子どもが境界性パーソナリティ障害の母親にも、同じ傾向がみられる。
境界性パーソナリティ障害や摂食障害、気分障害、依存症、解離性障害などについては、以前から、不安定な愛着の関与が指摘されてきた。
それに対して、ADHDは、遺伝要因の強い神経発達障害とされ、養育要因などまったく関係がないと、専門家たちも言い続けてきた。
ところが、遺伝子について調べ尽くされるにつれて、遺伝子の関与だけでは、とうてい説明がつかないということがはっきりし、近年では、遺伝要因と環境要因との相互作用による部分がかなり大きいと考えられるようになっている。中でも、養育環境の影響を受けることがわかってきたのだ。
■現代人の「生きづらさ」には愛着の問題が関わっている
たとえば、施設に保護された子どもでは、ADHDと診断される子どもの割合が、通常の何倍にもなる。虐待を受けた子どもでは、ADHDの発症リスクが大幅に高まるのだ。
この事実に対しては、ADHDだから虐待を受けやすいのだとか、親もADHDの傾向を持っているので、虐待が生じやすいのだと説明され、虐待によってADHDになるわけではないと、専門家たちも言い続けてきた。
だが、実際は違っていた。虐待は、脳の構造自体に異変を起こし、不注意や多動を含むさまざまな行動や精神の症状を生じ得るということが明白になっている。さらに、幼い頃に養子になることで養育者が交代しただけで、ADHDのリスクが数倍に高まるということもわかってきた。
ことに、虐待のケースにみられやすい「無秩序型」と呼ばれる非常に不安定な愛着を示す場合、その後、ADHD症状がみられるリスクを大幅に高めていた。しかも、親との愛着の安定性は、その子の神経機能障害の指標である認知機能よりも、ADHD症状を左右したのである。
それ以外にも、不安定な愛着がリスクファクターとなるものとして、依存症(薬物、ギャンブル、セックス、インターネットなど)、希死念慮、解離性障害、原因不明の身体疾患、慢性疼痛、虐待、DV、いじめ、離婚、非婚、セックスレスなどが挙げられる。
いずれも、今日の社会において問題となっていることばかりだ。
このように、現代人の生きづらさと苦悩の根底に、愛着の問題が関わっているということが明らかとなってきているのである。
———-
岡田 尊司(おかだ・たかし)
精神科医
1960年、香川県生まれ。京都大学医学部卒。岡田クリニック院長、日本心理教育センター顧問。『あなたの中の異常心理』(幻冬舎新書)、『母という病』(ポプラ社)など著書多数。小笠原慧のペンネームで小説家としても活動し、『あなたの人生、逆転させます』(新潮社)などの作品がある。
———-
引用先:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190929-00030108-president-soci
解決サポート
〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-6228-2767