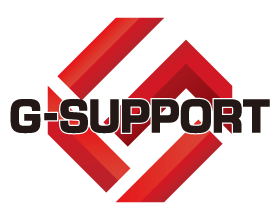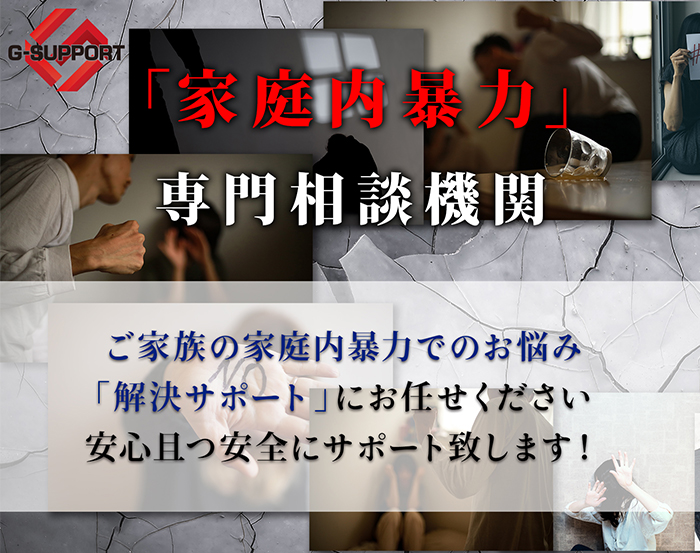ニュース情報
可視化されない「大人のひきこもり」~若者だけの問題で済まされない現実に迫る~
2015.12.27
「大人のひきこもり」という言葉が注目されているのか、取材や講演などの依頼が増えている。
筆者は約18年にわたって「ひきこもり」界隈を追いかけているが、毎日、当事者たちからメールが届く。ここ数年は、40代以上の相談が増えている実感がある。しかし、こうした現実は、多くの人に「見えていない」ためか、意外に知られていない。
ひきこもりが長期化・高年齢化
「大人のひきこもり」とは、いったい何なのか。
これまで「ひきこもり」というと、不登校の延長にある学校卒業後の「若者の問題」として語られることが多かった。しかし、ひきこもり中核層は確実に、その存在が見えにくいまま、長期化・高年齢化してきている。もはや、こうした状態にある本人たちのことを「若者」だけで語れないし、選別が行われてきたことによって、深刻な当事者ほど、ますます水面下に追いやられる弊害をうみだしている。
「ひきこもり」というと、よくドラマや映画などでは、カーテンを閉め切ってジメッとした部屋にこもるイメージで描かれる。しかし、現実には、部屋や家から外出できるかどうかで線引きすると、本質を見誤る。なぜなら、本人たちの多くは、コンビニや図書館などへは外出しているからだ。河川敷をよく散策している人も意外と多い。生きるために、仕方なく外に出ている人もいる。それは、本人たちの声を聞けば、よくわかる。
「ひきこもり」とは、家族以外との関わりがまったく途絶えてしまった、あるいは家族とさえもコミュニケーションが取れなくなってしまったなど、本人が社会から孤立した状態にあるかどうかで見なければいけない。
毎日届く悲痛な「SOSメール」
筆者の元には毎日、何人もの方からメールが寄せられてくる。しかも、メールの大半は、ひきこもっている本人や経験者、あるいは、社会と関わっていても先行きが不安定で「自分もそうなるかもしれない」と危惧を感じる“当事者予備軍”たちからの叫びだ。
ダイヤモンド・オンラインの『「引きこもり」するオトナたち』という連載は、当初半年の予定だったが、反響の大きさから6年以上続いていて、250回を超えた。記事を更新すると、1日に10通以上の声が届くこともある。1年365日、年末年始も関係ない。大みそかの除夜の鐘が鳴り響いている最中でも、メールは届く。
訴えてくる内容は、ほぼ共通している。「どこにも行き場がない」「周囲の視線が気になって人目を避けてしまう」「何もない自分を表現できない」「将来が見えない」などだ。
地方では、「外を歩くだけで不審者扱いされて怖い」と脅える人もいる。外の社会に、自分の存在を受け入れてくれたり、認めてくれたりする人たちがいないために、かつての友人や同級生などの人脈もだんだんと途切れて、遠のいてしまうのだ。
とくに心を動かされるのは、自宅から出られない、姿の見えない本人たちからのSOSを求めるメールだ。「生きていても社会に迷惑がかかるだけ」「死にたい」などと訴えてくる人も少なくない。
ひきこもり状態に陥るのには様々な理由がある。例えば、いじめや体罰、暴力、受験、就職活動の失敗、失業、事件事故、災害、親の介護、病気、LGBT等への偏見などだ。「ひきこもり」は、誰でも起こり得る状態であり、誰にとっても決して他人事ではない。だから、大事なのは、なぜそうなったのかではなく、どうして抜けられないのかという検証だ。
学校や社会などでさんざん傷つけられてきた当事者たちは、「もうこれ以上傷つけられたくない」し、自分も「他人を傷つけたくない」などと、自分の生命や尊厳を防御するために、場面回避を繰り返して撤退していく。やがて、生きる意欲や意義さえも失い、あきらめの境地に至ってしまった人たちだ。
しかし、メールを出してくれるということは、こうして様々な理由であきらめてしまった人たちが、再び社会との関係性をつくろうとして、ワンチャンスとの思いで勇気を出して動き出そうとしている証しでもある。
「どうしたらよいのかわからない」「小さな勇気すらわかなくなる」
典型的な例を紹介すると、こんな感じでメールが来る。40代の女性からの声だ。
メールを送るのも怖くて、ずいぶん悩みました。でも、今の私には、誰とのつながりもありません。どうしたら引きこもりから抜け出せるのか、きっかけが欲しいと思い、勇気を出してメールをすることにしました。人間関係が苦手で、孤立しています。何とかしなければと思うのですが、どうしたらよいのかわからないのです。
会うことのできない本人たちの中には「会うのが苦手」という人は少なくない。しかし、お互いが無理しない程度でやりとりするメールでなら、つながることはできる。「会わずに文字のみのコミュニケーション」ならストレスを感じることなくやりとりできることを、ひきこもっている本人たちが端的に教えてくれる。
誰に助けを求めればいいのか。
そもそも助けを求めていいのかすら、わからない。
声を出したいのに、ほんの小さな勇気すらわかなくなる。
このメールは、地方に住む別の男性当事者からのものだ。彼は、生活に困窮する実家から、都会での自立を夢見て、そんな思いをメールで明かしてくれた。本人や家族が直面する課題は、先行きの見えない「貧困問題」にも直結している。
内容は全般的に、「社会につながりたい」「親元から自立したい」「仕事をしたい」けれど、「どうしたらいいのかわからない」といった趣旨が多い。匿名性が高く、人目に触れて緊張することの少ないネットを通して、今の自分の状況を何とか打開したいという前向きな印象を受ける。しかし、彼らの背後には、ネットのできない人、携帯さえ持てない人たちもいる。
40歳以上は調査対象外、乏しい国のエビデンス
「大人のひきこもり」は、こうした社会的な課題であるにもかかわらず、国のエビデンス(データ的根拠)がほとんどない。

最も直近のデータである内閣府が2010年に行った調査では、全国に約70万人、予備軍も含めると225万人に上ると推計している。しかし、これも対象が15歳から39歳までの若者層限定のデータに過ぎない。
2013年以降の山形県や島根県の調査によれば、ひきこもり層に占める40代以上の割合は半数を超え、山梨県では6割に達した。民生委員を通じた自治体の間接調査とはいえ、エビデンスがない中での参考値として、高年齢化の傾向はすでに顕在化している。
内閣府の2010年の調査でも、35~39歳のひきこもり層が最も多かった。にもかかわらず、その後に打ち出した施策は、先を見据えた対策ではなく39歳以下に限ったものだった。
国の調査から5年が過ぎて、団塊ジュニアのボリューム層も40代を超えた。国の年齢上限を「39歳」で区切る現実にそぐわない調査やチグハグな施策が、現場で40歳以上のひきこもり状態の人たちを選別し、本人や家族を地域で孤立させて、潜在化につながる事態を招いたといえる。
「ひきこもり」を年齢で区切る根拠はどこにもない。なぜなら、「ひきこもり」の状態は、変わっていないからだ。
そもそものきっかけの多くは、(長期化によって2次的に疾患や障害を発症する事例はあるものの)社会的構造や人間関係の問題から離脱せざるを得なくなって社会に戻れなくなったことだ。高年齢化しているからといって、何でも精神疾患や障害が原因ではないかと思い込むことは、周囲が向き合うべき問題を見誤ることになる。
最近は、周囲の期待する「レール」から何らかの事情でいったん外れ、求人に応募しても落とされ続けた例も目立つ。やっと職に就けたとしても非正規や派遣、ブラック企業で、1日に10時間以上働いても月収10万円余りにしかならないような実態にあえいでいる働く世代も多い。支援などの相談窓口へ行っても、気合論や精神論ばかりで、「しんどい」などと弱音を見せると、精神科への受診を勧められて屈辱的だったという話も聞く。
浮かび上がった共通項、気遣いし過ぎて疲れてしまう心優しき人たち
そんな中で、先駆的なひきこもり施策を進める町田市保健所(東京都)が最近、ひきこもり当事者10人にヒアリングして、ケースごとの情報と共通に見られる状況等について整理した調査報告書を出した。
それぞれの事例を拾い上げていくと、興味深いことがわかる。「相手から声をかけてくれるほうが話しやすい」「小さなことでもホメてもらえると嬉しい」「アドバイスされるのが嫌。経験した人にしかわからない」「普通に接してくれる人が一番安心できた」「安心したのは自分のタイミングでいいと言ってくれたこと」「試しにという感じで見学から、保健師も同行してくれた」。これらはすべて当事者の声だ。
ひきこもり当事者たちにほぼ共通するのは、研ぎ澄まされた感受性を持ち、カンがいいために、人一倍、周囲の気持ちがわかり過ぎてしまうところである。それだけに、自分の望みを言い出せず、逆に相手に頼まれると断れず、気遣いし過ぎて疲れてしまう。自分さえ我慢すれば、すべて丸く収まるからと納得のできない思いを封じ込めて、社会から撤退していく、真面目な優しい心の持ち主という像が浮かんでくる。
考えていかなければいけないのは、こうしたセンシティブな感受性を持った人たちが、誰にも助けを求められないまま、あるいは「家の恥だから」「近所に知られたくないから」と考える家族に隠され、地域の中に埋もれてしまい、潜在化していくことにある。
当事者と家族たちが声を上げ始めた
実際には、メールでやりとりが継続できても、面会はできないという当事者が多い一方で、1通のメールをきっかけにして、同じような状況の仲間たちと出会い、元気になっていく人たちも少なくない。そこから、社会的な活動に関わったり、仕事に就いたりした事例がいくつも生まれている。
苦しいと訴えたり、助けを求めたり、自分に関係のありそうな情報を得ようとしたりすることは、社会からの関係性が閉ざされた状況にあるひきこもり本人や家族にとって、これから生きていくうえで重要な行動だ。
そして、利害のある関係者が提供する一方的な情報だけではなく、客観的で少し距離感のあるところからの情報のほうが、長年ひきこもってきた本人たちのアンテナに引っかかることも少なくない。それらの中から自分に必要な情報を選び取り、ある日、自らの意思で動き出そうと思い立つきっかけにもなり得る。
本人たちにとっては、自分でも役に立つことができたり、価値を認めてもらえたり、多様な関係性がつくれたりする安心できるコミュニティの情報に接するだけでも、将来の道筋が見えてきて、希望を感じることができるようだ。
ネガティブな誤解を解く「ひきこもり大学」
2013年8月から、「とらさん」(当時30代半ば)という当事者の発案で始まった「ひきこもり大学」と呼ばれる社会への発信活動は、またたくまに各地の当事者たちの間に普及していった。

ひきこもり大学とは、不登校やひきこもり状態にある/あったことのある人が講師となり、「ひきこもり」体験を通じた見識や知恵、メッセージなどを、関心のある人たちに向けて講義するもの。発案者とらさんのそもそもの思いは、「空白の期間」などとネガティブに受け止められがちな「ひきこもり」という状態像に、当事者ならではの捉え方を共有することを通じて「ひきこもり」期間を通じて得たものへの価値を見出し、様々なネガティブな誤解を解いていくことにあった。
このひきこもり大学は、支援団体や親の会などが当事者に行わせる「体験発表」や「成功体験報告」とは趣が異なる。当事者が自らの意思で希望し、これまで閉じ込めてきた思いや感情を自由に発信して、社会に伝えていく場だ。そこには、一方的に講師が話すだけでなく、参加者とともに、新しい社会参加の仕組みを考えていきたいという思いがある。だから、学部学科名も最初から用意された設定があるわけではなく、講師が自由にネーミングしている。実際、自己表現学部というクリスマスライヴや、対人恐怖学部というキャンプファイヤーも行われた。
当初、ひきこもり大学のアイデアは、「ひきこもりが問題でない未来を描く」というコンセプトに関心のある多様な人たちが集まる対話の場「ひきこもりフューチャーセッション[ 庵 IORI ]」の中で、当事者を主体に構想が練られた。庵では、本業を持つ普通の会社員たちがプロボノとして、ファシリテーター(対話の促進役)を務める。
庵は、2012年9月にスタートして以来、偶数月の第1日曜日に都内で開催されてきた。最近は100を超える参加者が集まり、そのうち6~7割が当事者で占められる。ひきこもり大学も、そんな庵の対話の場から生まれた当事者のアイデアのひとつだった。
都内に住む30代後半の男性は、周りに合わせるのが苦手な性格で、仕事が長続きせず、再就職はもう無理だとずっとあきらめていた。しかし、庵やひきこもり大学に参加したのをきっかけに、「いろいろな場に出かけ、発言していく繰り返しの中で、何とかなってしまった」と打ち明ける。いまは派遣の仕事に採用され、1年以上続いている。
そんな彼がこう話す。
「自分の話したことが相手に通じて、受け止めてくれる人がいる。自分の窮状を訴えて、レスポンスをきちんと得られる場が、当事者には必要です」
2015年度に入ると、家族会で唯一の全国組織である「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」(KHJ家族会)は、「ひきこもり大学KHJ全国キャラバン2015」(日本財団助成事業)を支部のある全国21カ所で展開した。こうして、居場所があまりない地方でも、KHJ家族会が開催を実現。地域に住む本人や家族からは「ありがたい」という声が聞かれ、地域で多様な参加者が関係性を作るプラットフォームの場にもなった。
今年10月には、KHJ家族会と庵のコラボによるファシリテーターを養成する講座(日本財団助成事業)で、新たにひきこもり経験者を中心に22人の(経験や親和性がある)ピア・ファシリテーターも誕生した。ひきこもり当事者が、相手の感じている障壁を見抜く力や空間の居心地への配慮、社会に役立ちたいという気持ちなどの点で、ファシリテーターに向いているというのは、1つの発見だった。
「ひきこもり対策後進県」山梨を動かした地方紙の連載
社会経験を経てひきこもっていた山梨県の永嶋聡さん(46)は昨年6月、庵などをきっかけに出てきて、地域の中で紹介を受けながら関係性を構築。この12月には、社会参加したい人のピアグループ的な場として準備中の一般社団法人「やまなしピアカフェ」の設立社員になり、起業するに至った。
このようなひきこもり本人と社会参加の関係を作る橋渡しをしたのが、地方紙などの地域のメディアだった。
KHJ家族会も当事者会も居場所もほとんどなく“ひきこもり対策後進県”といわれてきた山梨県が、わずか1年で大きく様変わりしようとしている。その背景には、山梨県で圧倒的な新聞購読率を誇る山梨日日新聞の存在があった。
同紙は2014年8月から「ひきこもり」を題材にした連載「扉の向こうへ 山梨発 ひきこもりを考える」をスタートさせた。この間、地域に埋もれていた数多くの本人や家族が出てきて、多様な人たちとの関係性をつくりだし、仲間たちとのコミュニティ活動も同時多発的に動き出すなど、地域の活性化につながる様々な波及効果をもたらした。「扉の向こうへ」取材班は、そんな1年近くにわたる連載記事を冊子にもまとめている。

一般的に記者は、目に見える現象であればわかりやすいから、記事にもしやすい。しかし、同紙によれば、取材班の打ち合わせで「新聞記者の仕事は、目に見えない課題を掘り起こして、社会や読者に問うこと。取材を尽くして紙面に表すのが、新聞の役割なのではないかという原点に立ち返ろう」と話し合い、連載が生まれたという。
「ひきこもり」は、全国どこにでもある課題や現象ではあるものの、地域性の強い所では、家族が声を上げられない現実もある。そんな中で、「地方紙の果たす役割があるのではないか」と考えさせられる出来事でもあった。
ふだん、ネットをしていない人たちに向かって、新聞のような旧来型のメディアを使った発信を展開していくことで、「大人のひきこもり」への理解者を少しでも増やしていくことは、「支援」と言われるだけで身構えてしまいがちな本人たちの「見えない障壁」を取り除くためのカギを握っていると思えるのだ。
山梨県は今年、各市町村や当事者会も含めた83団体と連携して、ひきこもり対策に取り組む「ひきこもり支援連絡会議」を発足。相談窓口である「ひきこもり地域支援センター」も開設し、山形県、島根県に続いて、「ひきこもり実態調査」も行った。
しかし、そもそもは、ある当事者の「庵みたいな居場所をつくりたい」という思いから始まった。そんな思いに応えるように、家族会と当事者会が生まれ、民間の人たちや大学の教員らが反応。地域のメディアの記者が、熱意を持った民と官の個人を紹介し合ってつないでいく触媒的役割を果たした。そのうねりが、やがて行政を突き動かすという好循環を生み出したともいえる。
典型的な過疎地だった秋田県藤里町の社会福祉協議会も、2011年までに全国初の全戸調査を行い、11人に1人がひきこもり状態にあったという調査報告をまとめた。また、当事者たちの居場所や仕事を創り出すことで、地域の掘り起こしにつながった。自治体のモデル事業として、同町社協の取り組みはすっかり有名になり、当時の事務局長だった菊池まゆみさんは、いまや全国を飛び回る。しかし、同町社協がこうして全国区になった背景には、実は陽の当たらないときから秋田県の地方紙「秋田魁新報」が、連載を組んで社協の取り組みに伴走してきたことにある。
つながりを求めている当事者に社会の側から近づこう
ここまで紹介してきたように可視化できているのは、つながれる人たちからまず社会とつながっていき、声をかけあったりしながら元気になっていく、“変化”する人たちの存在だった。でも、忘れてはいけないのは、おそるおそる勇気を出して来てくれた人たちの背後には、たくさんの姿の見えない人たちがいるということだ。
多くの当事者たちが求めているのは、社会にいる人たちとのフラットなつながりであり、そうした多様な人たちとつなげてくれる触媒的な人たちの存在だ。
本当は再び、つながりたいと願っている人たちのためにも、「ひきこもり」に対する偏見の水位を少しでも下げられるよう、社会の側から近づいて、みんなで一緒に考えていくことが、これからますます大切になってきている。
記事URL
http://bylines.news.yahoo.co.jp/masakiikegami/20151227-00052595/
解決サポート
〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-6228-2767