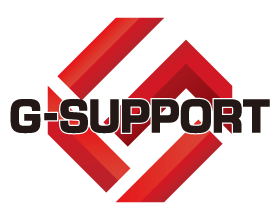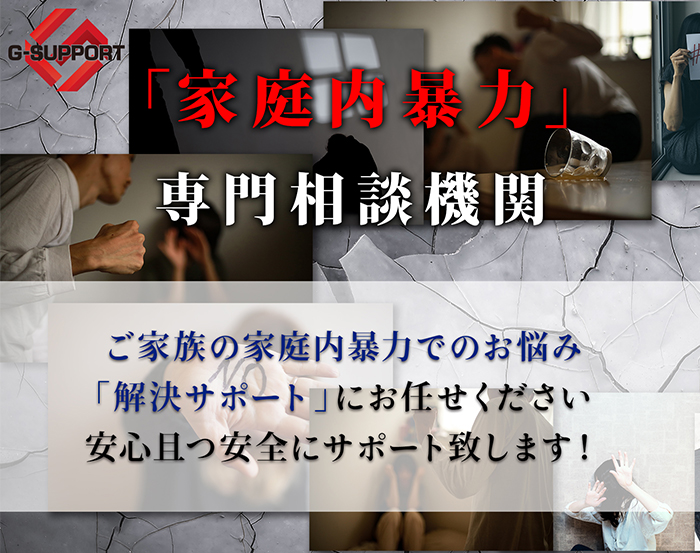ニュース情報
山梨を引きこもり対策先進県にした 地方紙の本気記事
2015.07.30
地方紙の果たす役割は、ますます重要になりつつある。
“ひきこもり対策後進県”といわれてきた山梨県は、わずか1年で“ひきこもり対策先進県”へと変貌しようとしている。
その背景にあるのが、山梨県で圧倒的な新聞購読率を誇る「山梨日日新聞」の存在だ。
同紙を発行する山梨日日新聞社は、2014年8月から「ひきこもり」を題材にした連載「山梨発 ひきこもりを考える~扉の向こうへ」をスタートさせた。
この間、引きこもり界隈の取材を長年続けてきた筆者も目を見張るほど、地域に埋もれていた数多くの当事者や家族が出てきて、多様な人たちとの関係性をつくりだし、仲間たちとのコミュニティ活動も同時多発的に動き出すなど、地域の活性化につながる様々な波及効果をもたらした。
1年弱で約130本の記事を出稿
読者からは終了を惜しむ声も
山梨日日新聞「扉の向こうへ」取材班の記事をまとめた冊子。出版を望む声も
拡大画像表示
「扉の向こうへ」取材班は、そんな1年近くにわたる連載記事をこのほど冊子にまとめた(写真1)。
冊子をめくっていると、様々なことが思い出されてきて感慨深いものがある。
取材班による最初の記事は、2014年8月1日付け<「山梨親の会」設立へ、16日に講演会へ>。
1年ほど前、筆者も、ひきこもり家族会の全国組織「全国ひきこもりKHJ家族会連合会」の池田佳世代表から、山梨で家族会の支部をつくるので、一緒に講演してほしいと依頼された。
会場の県立図書館や筆者らの日程の都合で、たまたま調整できたのが、8月16日。「お盆だから人が来ないのではないか」などと、池田代表は心配していたものの、実際には100人以上の家族や当事者らが参加して、椅子を追加で運び入れるほど盛況だった。この講演会が、第一歩だった。
最初に取材班の記者に会ったのは、2014年6月。東京で「庵」(ひきこもりフューチャーセッション)が開催される前に待ち合わせて、取材を受けた。
偶数月の第1日曜日、ひきこもり当事者たちの思いを真ん中に置いて、多様な人たちとの対話の場をつくりだしている「庵」に、同紙の記者も参加してくれた。
この「扉の向こうへ」取材班に関わった記者は、延べ6人。昨年8月以降、連載は第9部まで続き、プロローグとエピローグを入れると計67回で、アンケートやグラフィック、ストレートニュースなども含めると、出稿記事は約130本に上る。
第9部まで続いた連載は、今年6月で区切りをつけて終了したものの、取材班の高橋一永担当デスクによると、「これで終わりになるの?」「もう取材しないんですか?」などの問い合わせが相次いだという。
地域に埋もれた声なき声を拾う――
新聞の原点に立ち返った企画
最初に取り上げた2014年8月1日付けの記事(山梨日日新聞「扉の向こうへ」取材班)
拡大画像表示
連載のきっかけは、通年企画の取材班の打ち合わせから生まれた。
「隣の息子さん、東京から帰ってきたはずなのに、最近見ないよねとか、あの家の娘さん、実家に戻ってきたはずなのに姿を見ないよねとか、取材先で、そんな話をチラホラ聞くようになったんです。引きこもりというのは、社会のあらゆる問題と地下でつながっているのではないか。引きこもりは目に見えなくなって、地域に埋もれてしまい、声も上げられない。声なき声を拾い上げるのが新聞の役割。突っ込んで取材してみないか。そう編集局長からの提案もあって、メンバー一同でやってみようということになりました」(高橋担当デスク)
一般的に記者は、目に見える現象であればわかりやすいから、記事にもしやすい。
「でも、新聞記者の仕事は、目に見えない課題を掘り起こして、社会や読者に問うこと。取材を尽くして紙面に表すのが、新聞の役割なのではないかという原点に立ち返ろうというのが、始まりだったんです」(高橋担当デスク)
「引きこもり」は、全国どこにでもある課題や現象ではあるものの、地域性の強い所では、家族が声を上げられない現実もある。
そんな中で、地方紙の果たす役割があるのではないかと、高橋担当デスクは指摘する。
「地域性のあるところで、“自分たちだけではないんだ”と感じることのできる場所が公にできて良かったと、何人もの読者の方からご意見、ご感想をいただきました。こういう企画をやってくれたおかげで、引きこもりは恥ずかしいことではないんだ、責められるべきことではないんだということがわかったと。一方で、怠けだ、親の甘やかしだという声もあり、電話でご理解をいただいてきました。連載担当デスクになって5年目になりますが、これほど大きな反響をいただいたのは初めてです」
当事者たちの声が届き
ついに県・市町村も動き始めた
ひきこもり大学の可能性を紹介した第9部の連載(山梨日日新聞「扉の向こうへ」取材班)
拡大画像表示
「庵」からアイデアが生まれ、当事者自らが自由に親や家族に講義する「ひきこもり大学」についても、連載の第9部で取り上げられた。
今年6月8日付の第1回の紙面に、こんな象徴的なシーンが紹介されている。
「他人からは無駄に見える時間も、決して無駄ではない」
ひきこもり大学に出会い、胸に不安を抱えながら参加したリュウさん(25歳)は、とつとつと過去を語るそんな講師の言葉に、心が震えた。
<いつか自分もあの人と「同じ場所」に行きたいと思った>
まさに「経験を価値に変えたい」と、ひきこもり大学を発案し、動き出した当事者たちの思いや概念が、そこにある。
引きこもる人たちが長い間、否定的に思ってきた“空白の履歴”の価値観を肯定していいんだよと思えるような社会になれば、外に出て行きやすくなるし、自信も持てる。
そして、ようやく県も動いた。
山梨県は各市町村と連携して、引きこもり対策に取り組む「ひきこもり支援連絡会議」を発足。画期的なのは、家族会や当事者も含めた83団体の組織が生まれ、横の連携をとることになったことだ。
同紙も29日付の1面トップで、このニュースを報じた。
また、県では、引きこもり状態になっている人たちの性別や年齢層、家族構成などの実態調査にも乗り出した。早ければ、9月にも結果が報告されるという。
遅ればせながら、「ひきこもり地域支援センター」も開設されることが決まった。
これまで、県内のすべての自治体が「引きこもり実態調査」をしたことがなく、引きこもりに特化した支援策もなかった“後進県”だったことを考えると、大きな変化である。
「山梨では、民の動きが加速度的に広がっている感じがします。行政もようやく動き出したということも、評価できるところだと思います。ただ、これから実効性のある施策に結びつくのかをチェックして、今後、自治体でしかできない施策を推進して行けるよう、郷土の新聞としての役割を果たしていきたいと思っています」(高橋担当デスク)
秋田県藤里町社会福祉協議会のひきこもり施策は、いまや自治体のモデル事業として、すっかり有名になった。しかし、藤里町の社協がこうして全国区になったのも、実は陽の当たらないときから秋田県の新聞「秋田魁新報」が連載を組んで伴走してきたからだ。
山梨でも、当事者たちが中心になり、県内の3つの大学の協力も得て、30日には、藤里町から社協の菊池さんを招いて藤里方式から学ぶ山梨のひきこもり支援の未来」を開く。
これまでは手弁当でイベントを企画し、主催してきた当事者たちにも、今回は報酬が支払われることになったという。
全国ひきこもり家族会の支部も、ひきこもり当事者会も居場所もほとんどなかった県が、わずか1年で大きく様変わりしようとしている。
取材を終えた記者たちの思い
「再起した人のその目は優しい」
今年1月16日付の「記者の思い」には、取材班に携わった4人の記者の思いが綴られている。
<取材を通じて知り合ったひきこもり経験者の多くは、個性あふれる人ばかりだ。「ひきこもり外交官」と自称し、全国各地の支援の動きを視察して回る男性。人に雇われない仕事を探し、ネットビジネスで名をはせた女性。性的マイノリティーを自負する人…。苦難を伴いながら自分と向き合い、時に自暴自棄になったり、家族に矛先を向けたりもする。しかし、その体験を経て再起した人々はバイタリティーにあふれている。そして、その目は優しい>(古守彩記者)
<人の心の中で起きている変化は、目に見えない。親の会で母親が話した「世間の目が変わってきている」という動きは、この企画だけがきっかけではないと思う。だが、「新聞を読んで考えが変わった」「記事をきっかけに動き出せた」―。そんな感想を聞いたとき、言葉を預けてくれた当事者や家族に、少しだけ報いることができたのではないか、と感じる>(木下澄香記者)
そんな県内外の状況や様々な事例を丹念に追いかけてきた同取材班の貴重な冊子は、残念ながらわずか50部しか刷っていないという。ただ、いずれ出版化されて、山梨の報告が広く全国に読まれることを期待したい。
記事URL
http://diamond.jp/articles/-/75767
解決サポート
〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-6228-2767