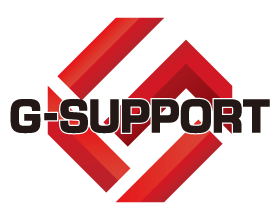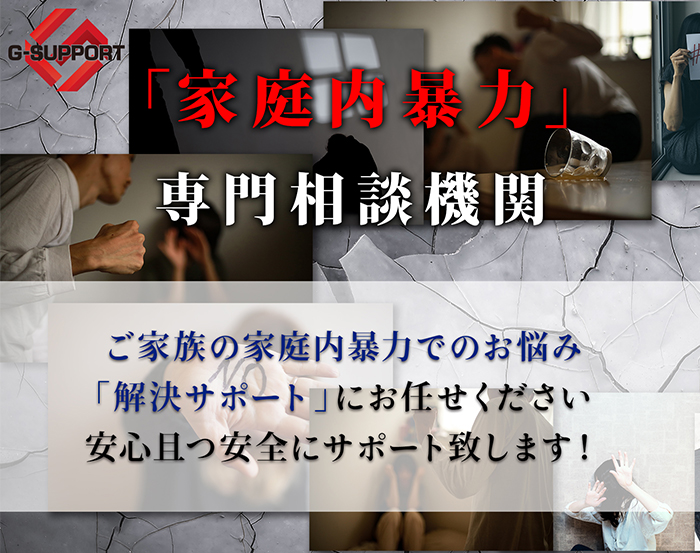ニュース情報
酷暑のゴミ屋敷、冷凍ペットボトルで命をつなぐ40代女性の孤独
2019.07.09
年間3万人といわれる孤独死者。その個々の人生にスポットを当てるべく、ノンフィクション作家の菅野久美子さん(37)が取材を始めて4年が経つ。大量の蝿が飛び交い、無数の蛆虫が這いまわる。そんな過酷な死の現場に、かつてどんな「生」があったのか。このほど、『超孤独死社会 特殊清掃現場をたどる』(毎日新聞出版刊)を上梓した菅野さんに聞いた。
1000万人の孤独死予備軍
――人生100年時代と言われるなか、孤独死、8050問題、中高年の引きこもりと、様々な社会問題が露見しています。
菅野:私の試算ですと、日本で現在およそ1000万人が孤立状態にあります。これは、日本人の10人に1人という非常に大きな割合です。孤独死とは、家で一人、誰にも看取られずに亡くなることを指しますが、その約8割に見られるのが、ゴミを溜め込んだり、必要な食事を摂らなかったり、医療を拒否するなどして、自身の健康を悪化させる「セルフネグレクト」です。
“緩やかな自殺”ともいわれるセルフネグレクトに陥ると、周囲に助けを求めることもなく、社会から静かにフェードアウトしていく。近隣住民から奇異な目で見られていたり、遺族がいてもなるべく関わりたくないというケースが多々あります。そのため、彼らの遺体は警察によってひっそりと運び出され、遺品はほとんどがゴミとして処理されます。
――『超孤独死社会』では、孤独死現場の「特殊清掃」がテーマとして挙げられていますね。
菅野:特殊清掃は、遺体発見が遅れたために腐敗が進み、ダメージを受けた部屋や、殺人事件や死亡事故、自殺などが発生した凄惨な現場の現状回復を手掛ける清掃業です。そして、この特殊清掃のほとんどを占めるのが孤独死なんです。
孤独死が発生すると、近隣住民はその強烈な臭いで大騒ぎとなり、また、マンションの管理会社や大家はすぐに臭いを消さなければと慌てふためく。そうして依頼されるのが特殊清掃業者です。とくに孤独死の最も多く発生する夏場は、特殊清掃業者にとってかき入れ時で、中には現場から現場へ飛び回り、2ヵ月ほど不休で働き続ける業者もあります。
虫たちが蠢いている
――菅野さんは、特殊清掃人と共に、実際の特殊清掃の現場に立ち会って取材を進めました。そうして綴られた、あまりに凄惨な現場描写に息を呑みます。
———-
空気は滞留し、重々しくそして、ねっとりとしていて、澱んでいる。その中を虫たちが、我が物顔で闊歩する。カサカサカサカサという音だけが不気味な静寂の中で響いていた。(中略)部屋の真ん中にはベージュの絨毯と、その上に染みだらけの布団が敷いてあった。布団には黒々とした体液がぐっしょりと染みわたっている。ここで亡くなったのは明らかだった。(『超孤独死社会』より)
———-
菅野:初めて入った孤独死現場が、かなり強烈なケースだったんです。夏場にもかかわらず発見が1ヵ月も遅れたために、マンション一棟全体に死臭が移ってしまっていました。亡くなったのは70代の男性で、部屋は足の踏み場もないゴミ屋敷。床には頭皮の肉片や髪の毛がべったりとへばりついていて、とてつもない臭いが鼻の孔の中まで染みついていく。
その部屋の隣には普通の女子大生が住んでいたんです。普通の生活が営まれている、その壁一枚向こうでは、死体に無数の蝿や蛆虫が群がっている。それが現代日本のリアルなんだと、まざまざと感じました。だからこそ、ありのままを描写しています。
これは、将来の自分
ただ、取材を重ねるうちに、真の問題は、こうしたグロテスクな惨状にはないのではと思うようになったんです。現場に残された遺品からは、故人の生前の姿を感じることができました。彼らは何らかの事情で孤立し、人生に行き詰まり、生きづらさを抱えていた。私にも引きこもりの過去があり、社会をうまく生きられなかった経験があります。彼らと私は、どう違うんだろう。私は、ただ運が良かっただけではないのでしょうか。
著書や記事でこうした孤独死の現状を寄稿すると、多くの反響をいただきました。そして予想外にも、寄せられた声の半数以上が、私がそう感じたように、「これは、将来の自分」という反応だったのです。
一通のメールが届いた
――孤独死する人たちは、生前どのような生活を送っていたのか。それを知るために、菅野さんは、ゴミに埋もれて暮らす人々の家を何度も訪ねたといいます。
菅野:「私も孤独死するかもしれない」。今年6月末、私はある女性からダイレクトメールをいただき、彼女に会うために九州地方のある県に向かいました。待ち合わせに現れたその女性は40代で、体重が30kgほどでやせ細った姿でした。話を聞くと、もう3日も何も食べていないと言います。
しぶる彼女を説得して自宅アパートのドアを開けるや、むわっとした熱気が押し寄せてきました。東京とはくらべものにならない高湿度で、全身の皮膚にじめじめとした湿気がまとわりつきます。6畳のワンルームはモノとゴミで埋め尽くされ、窓も開けられない状態でした。
部屋の中心に女性が小さく丸まって寝るだけのスペースがちょこんと空いていました。その周りに大量に転がっている空っぽのペットボトルが目につきました。彼女曰く、それらはコンビニで買った冷凍ペットボトル。エアコンが機能せず、一日3本の冷凍ペットボトルを体に当てて冷やし、暑さをしのいでいました。
その女性はパワハラで精神を病んで勤め先を休業し、家に引きこもるようになったそうです。1分100円ほどの電話占いに依存し、借金は400万円にまでふくらんでいきました。傷病手当金が20万円支給されますが、そこから借金の返済分、家賃と光熱費が引かれ、毎日冷凍ペットボトル3本とお弁当2個を買って日々をやり過ごしている。そんな生活がもう1年続いていました。
夏本番を迎えて室温がさらに上がり、これほど体力の落ちた状態では、最悪の事態も考えられます。そんな生命にかかわる状況ですが、彼女は役所にも親にも助けを求めていませんでした。役所に相談すると親に連絡が行ってしまう。「親には死んでも知られたくない」。そうかたくなでした。
働き盛りであっても
――孤独死というと高齢者のイメージがありますが、若い世代にも他人事ではありません。
菅野:孤独死は、30~40代の働き盛りにも十分起こりうる問題です。それをもっと知ってほしいと思っています。ただ、こうした現役世代は長く引きこもっているわけではありません。失業や病気、離婚、失恋などによって、ある日、ぽきりと折れて引きこもりになってしまう。おカネをちゃんと持っているケースも多く、社会から孤立しているのを発見するのは困難なのが現状です。
前出の女性も、一年前には働いていたんです。傷病手当金ももらっているので、社協(社会福祉協議会)も、普通に生活しているだろうと思ってしまう。本人も家に訪問されるのを嫌がるので、誰もゴミ屋敷化に気づけないわけです。会社の人に会いたくないと、昼は家にこもり、夜にひっそりと買い物に出かけていました。
解決の処方箋はないのか
それではなぜ、彼女は私にSOSを出したのかというと、彼女の中には相反する思いがありました。このまま死んでもいいけれど、何か変わりたい。ここから飛び出したい。それを邪魔するのが、「この状況を近所の人や職場の関係者や親族に知られたくない」「迷惑をかけたくない」という感情で、これはもう、私みたいな無関係の人間がかかわるしかないのではと思うんです。そこに糸口があるかもしれないと考えています。現に彼女の場合は、しがらみの多い居住地の九州ではなく、東京の民間の生活サポート団体に繋ぐことで、解決の道筋を立てているところです。
単身世帯は年々増加し、2030年には、3世帯に1世帯が単身世帯になると推察されています。ただ、行政や技術的サポートもただ手をこまねいているわけではなく、AIやITを利用した見守りや、緊急通報システムの導入、レンタル家族による無縁者サポートなど対策が進んでいます。これは著書の中で詳しく述べています。
孤独死は、社会を構成する私たち一人一人の問題です。無縁社会が押し寄せる今、必ずしも家族でなくてもいい。九州の彼女のように、苦しくなって、他者に助けを求めることは決して恥ずかしいことではないんです。だって誰もが、セルフネグレクトに陥る可能性があるのですから。だから、同じような状況になっている人は、孤独死する前に、勇気を持ってSOSを出して欲しいと思います。
それと同時に、身近な人がセルフネグレクトに陥っていないか、そのちょっとした変化に気づいてあげて、社会から孤立する前に手を差し伸べることで、確実に孤独死は減るはずです。
引用先:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190709-00065702-gendaibiz-soci
解決サポート
〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-6228-2767