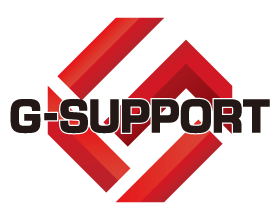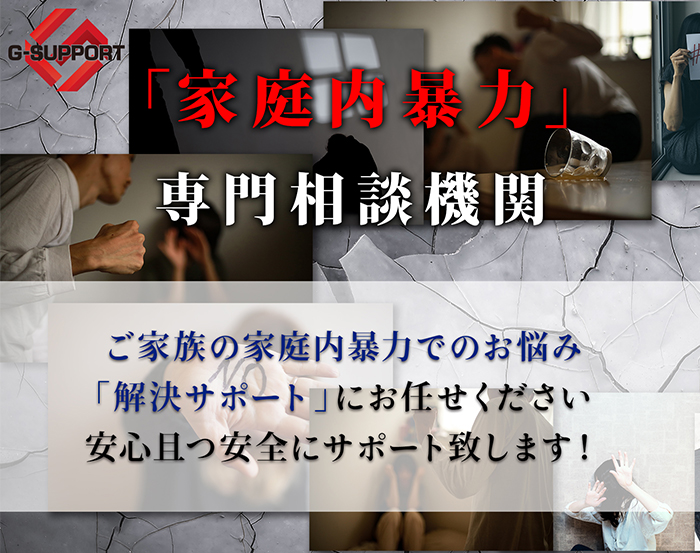ニュース情報
私はこうして「ひきこもり地獄」から脱却した――“生還者”が明かす実体験
2019.06.13
トイレ支配から親支配へ。「負のスパイラル」を辿るひきこもり地獄からの脱却は容易なことではない。ならば、ひきこもり生活からの「生還者」の実体験に耳を傾けてみるしかあるまい。
「32歳までの10年間、私はひきこもっていました」
こう振り返るのは、「ひきこもり新聞」編集長の木村ナオヒロ氏(35)だ。
「大学卒業後、弁護士を目指し、外界を遮断して勉強していたせいか鬱状態に。そんな私を見かねて警察を連れてきた親と大喧嘩したこともありました。私は自分のことをひきこもりだとは思っていなかったんです。だから、なんてひどいことをするんだと親に腹が立った。結果的に専門家の本に出会ったことで、自分はひきこもりなんだ、このままじゃまずいと気付くことができましたが……」
自覚さえないひきこもりがいるのだから、そこから抜け出すのは至難の業であることがよく分かる。
「肩書き」を持つこと
「私は18歳の後半から24歳まで、完全にひきこもっていました」
と、続けて現在31歳の男性が証言する。
「機械工場で働いたものの、コミュニケーションをとるのが苦手だったので、同僚から『知的障害なんじゃないの』などと言われ、他人と接するのが怖くなった。5カ月で辞めて完全なひきこもりが始まりました」
彼は『完全自殺マニュアル』を読むところまで追い詰められながらも、
「自分を変えられないかとも考え続けていました。そこで、誰にも会わなくて済む通信制の放送大学に入ってみることにしたんです。これが大きなきっかけとなりました。大学生という『肩書き』が持てたことで心の持ちようが変わり、外に出やすくなった。『無職で話すことが何もない』のと、『年齢的に遅れていますが大学生なんです』と言えるのとでは、気分が全く違うんです」
自ら大学に入ろうと思えたこの男性は、ひきこもりの中でも「軽い」ほうと言えるのかもしれない。だが彼の話は、ひきこもりの人にとって肩書き、つまり社会と接点があると思えることがとても重要なのだと示唆していると言えよう。
〈死に至る病とは絶望である〉(キェルケゴール)
孤立という名の絶望。この病をいかに遠ざけるかが、現代日本社会に重く突き付けられている。
引用先:https://www.dailyshincho.jp/article/2019/06150558/?all=1
解決サポート
〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-6228-2767