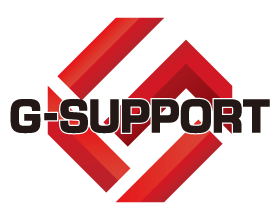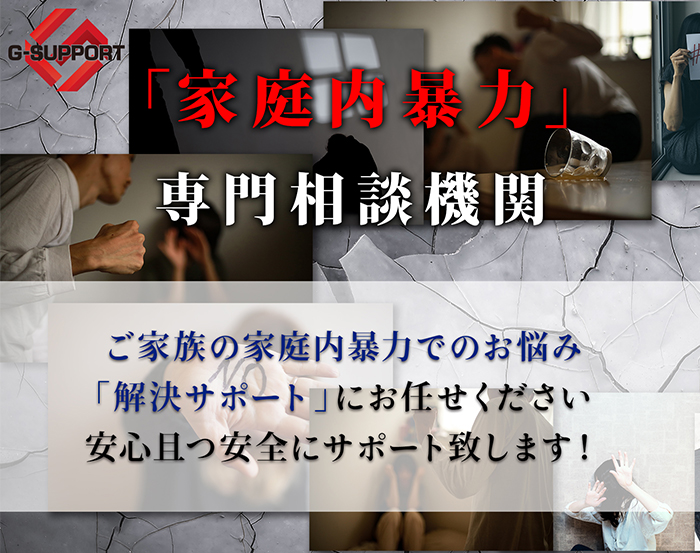ニュース情報
難関国立大卒、大手企業内定し30年以上ひきこもり 57歳男性が社会に問う「恥とは何なのか」
2019.06.25
ひきこもり状態だった50代の男がスクールバスを待つ子たちの列に刃物を振り回し、20人を殺傷し自殺。その3日後、「運動会の音がうるさい」と苛立っていた40代のひきこもりの長男を、元事務次官の男が殺害した。川崎市と東京・練馬で連鎖するように起きた2つの事件から、もうすぐ1カ月が経とうとしている。ひきこもりや「8050問題」にこれほど注目が集まったことはこれまで無かっただろう。23歳から30年以上、断続的にひきこもり状態が続き、「ぼそっと池井多」という名前で活動する男性(57)は「事件から少し時間が経った今だからこそ、当事者として伝えたいことがある」と、自身の体験を語り始めた。事件から何を学ぶべきなのか。
6月1日、ひきこもりの長男(44)を父親が殺害した――。そのニュースをテレビで見ながら、池井多さんの頭にふと浮かんだのは4、5歳ごろの家の中の風景だった。
「夕食は何を食べたい?」と母に聞かれ、「何でもいい」と答えた。
「じゃあ、ナポリタンスパゲッティーは?」
うんとうなずく。こうやって聞いてくるときも、母の中には既に決まった答えがあることはわかっていた。食べたいわけでもなく、出されても食は進まない。それを見た母は怒って、平手で頬を数回叩かれた。「食べたくないなら食べなくていい」と、スパゲッティーは取り上げられ、シンクに捨てられてしまった。
仕事から帰ってきた父に、母はうそをつく。
「この子が『こんなもの食えるか!』ってシンクに捨てちゃったのよ。お父さん、殴ってやって」
台所の床に座らされ、背中を丸めて両腕で頭を抱えた。両親の顔は見えず、父親がズボンのベルトを抜くキュッという音がする。恐怖と屈辱の中、背中をベルトで数発打たれ痛みが走った。夕食のメニューに限らず、理不尽な“制裁”を受けることは日常だった。今振り返ると、あれは母が「あなたは誰を信じるの?」と父を試す踏み絵でもあった。手を下す父はどんな表情だったのだろう。何を考えていたのだろうか。
殺された40代の長男と自分がダブって見えた。一方で殺人者となった父親への「どんなことがあっても殺してはダメだ」という批判も、薄っぺらく感じた。
事件を受け、当事者団体や支援団体などがひきこもりへの偏見を助長するような報道を控えるよう声明を発表。しかし、そこに留まってはいけないとも感じると池井多さんは言う。
「自分は被害者になり得る。それだけじゃなく、加害者にもなり得ると感じます。誰だって凶暴な気持ちになることはあり、そういう意味では私だって犯罪者予備軍なのでしょう。実際に川崎事件の後は当事者仲間から、明日は自分があのようなことをしてしまうのではないかと不安でたまらないというメッセージがたくさん届きました。事件から時間を経た今だからこそ『清く正しく美しいひきこもりだけではない』ということを伝えたい。私が知る中にも、親が資産家でスポーツカーを乗り回し、派手なスーツを着て複数の女性を連れ歩くようないわゆる“道楽息子”もいますし、暴力的で壁は穴だらけ、両親もアザだらけという状態の家もあり、そういう人たちは当事者会にもなかなか顔を出しません。『今日殺すか、明日殺されるか』という極限の状態で悩んでいる人たちを黙殺せずに対応を考えていかなければいけない。犯罪者予備軍と、実際に犯罪を犯す人の間には千里の隔たりがあると思うのです」(池井多さん)
池井多さんは、8050問題を当事者の立場で考える「ひ老会(ひきこもりと老いを考える会)」や、子の立場・親の立場から互いの本音をぶつけていく「ひきこもり親子 公開対論」などのイベントを開くほか、「GHO(世界ひきこもり機構)」という団体を立ち上げ、SNSなどを通してインタビューした世界のひきこもり当事者の声を発信をしている。この日もきちんと櫛でとかされた髪、清潔感のある半袖のシャツを羽織り、時折、含蓄あるジョークを織り交ぜながらゆっくりと語る様子は“部長の休日”風でさえある。3ヵ国語に堪能で、バイオリンとピアノもひける。「ひきこもり」と言われて違和感を覚えるのは、記者自身がステレオタイプなひきこもり像を持っていたからだろう。一口にひきこもりといっても多様である。それを体現するかのような存在だ。
しかも、時間とともにその状態も変わっていく。池井多さんは大学時代に「外こもり(自宅以外の場所でひきこもること)」、30代で「ガチこもり(外との関わりを断ち、自宅・自室から出ない状態)」を経験し、現在も必要なとき以外では外出しない「ひきこもり」だ。何をきっかけに、どんな思いで過ごしてきたのか。
初めて自宅から出られなくなったのは23歳のときだった。就職が内定していた大手企業の入社式を目前に控えた朝だった。布団から起きられず、一歩も外に出られなくなった。内定を辞退し、2年間は大学を留年。アパートから家賃の安い寮に移り、学費を稼ぐために必死で外に這い出て、塾でアルバイトをした。精神科でうつ病と診断を受け、治療も始めた。しかし、卒業するとまた動けなくなった。
「挫折体験をきっかけにひきこもる人は多いのですが、私はそうではありません。当時は理由もわからず、どうしていつも自分はこうなってしまうのだろうと苦しんでいました。後になって、母親が望むような人生を歩いていくことを拒否していたのだと気付きました」
父は高卒で会社員になり、四年制大学を卒業した母は自宅で学習塾を営んでいた。物心ついたときから母は父に聞こえるように、
「お父さんみたいになっちゃいけない。○○大学に入りなさい」
と難関国立大学の名前を繰り返した。英才教育として幼少期からバイオリンを習わされ、学校のテストは98点でも「なぜ100点じゃないの」と責め立てられた。思い通りにならないことがあるたびに、母は包丁を手に
「お母さん、死んでやるからね」
と脅された。その言葉は「お前を殺してやる」と言われるよりも何倍も怖く、身動きが取れなくなった。小学校低学年には死にたいと思うようになった。母が選んだ中高一貫校に通ったが、そこで出会った同級生は何代も続く家元の子や資産家、医者の子など生活レベルの違う家の子ばかり。強迫神経症に悩まされながら、なんとかコミュニティーに食い入ろうと、高校では生徒会長も務めた。
大学の合格発表は1人で見に行った。自分の受験番号を確認し、合格を知って人生の宿題をやり終えたと感じた。そして、母と子の関係をひっくり返してやりたい、これまでの苦痛を与えてきたことを謝ってもらいたいと手ぐすね引きながら帰宅した。
「あの大学は英語のレベルが高いから、明日から英語を勉強しなさい。お前なんか到底ついていけないんだから」
合格を伝えた直後の母の言葉に、何かがプツッと切れてしまった。どんなに走っても、報酬が無いどころか、ゴールテープはどんどん先に行ってしまう。
「頑張っても損だという感覚がこのときに生まれたのかもしれません。大学では授業にも出ず、キャンパスで友達をつくることもなく、バイトで資金を稼いでは海外に逃亡していました。母が望むレールを歩くのがバカらしくなったんです」
それが「外こもり」の始まりだった。インドの奥地や中国、中近東。東南アジアにある安宿の一室で本を読んだり、物を書いたり寝たりしながら、1日1回だけ食事を取る。観光地を見て回ったり、ショッピングや食べ歩きを楽しむことはない。母親が嫌な顔をすればするほど、海外へ逃げた。それが面白がられたのか、就職活動では学生から人気の企業としてランキング上位にいるような大手3社から内定を得た。それでも仕事をすることを体が拒否した。
大学卒業後に再度ひきこもるようになったときは自殺も考えたが、幼少のころにテレビで内戦や貧困、疫病などに苦しむアフリカの子どもたちが放送されるたびに、母親からいつも
「ご覧なさい。あの子たちはこんなに不幸なのよ……。それに比べて、あなたは食べ物も学用品も与えられて何不自由なく暮らしているのに、今日も怠けていたじゃない」
と責められていたことを思い出し、アフリカに渡った。どうせ死ぬなら本当に不幸な人を見るべきだと考えたからだ。カイロやナイロビに6カ月ずつ、南アフリカで1年など各地の安宿に滞在しながら、外こもりは5年近く続いた。外界との接触が少ない生活の中でも、宿を拠点に売春を営む女性たちや物売りをする子どもたちと話すこともあり、貧しくても不幸ではないと感じた。それどころか子どもたちは天真爛漫で、日本よりストレスが少ないようにさえ見えた。
帰国してから知人のすすめで、アフリカで見聞きしたものを文章にすると、ジャーナリストとして賞を受けた。国際ジャーナリストという肩書で働くようになったが、次第に仕事が苦しくなり、恩師の急逝などをきっかけに「ガチこもり」となった。カーテンを締めても、光が揺らめくのを見ると、その外に人の行き来を感じ「世界の動きから自分だけが置いていかれている」と苦しくなる。電灯の光でも肌がピリピリと痛む気がして、雨戸を閉めてろうそくの明かりだけで生活した。風呂も1カ月は入らない。食事は深夜にスーパーで買いだめしたカップラーメンを1日1回食べる。そんな日が4年続いた。
以前は家族で暮らしていた3LDKの団地に独りで住んでいたため、家賃は6万8千円。貯金も底をつき、ホームレスになる覚悟をして場所まで決めていたが、病院のケースワーカーの勧めで家賃の安い1Kの部屋に引っ越し、生活保護を受けることにした。
いまも週に1回程度、当事者イベントなどで必要なときにしか外出しない。「子どもが部屋から出てこない」という親から相談を受け、同じひきこもり当事者として会いに行き、ドアの外から話しかけ話を聞くこともある。当事者の声を社会に伝える活動は、フランスやイタリアほか世界中のひきこもりにまで対象を広げ、多言語に翻訳した記事を発信している。室内にいながら世界とつながっているのだ。
「ずっと海外とやり取りをしていて、久しぶりに外に出て日本語の会話を聞くと『帰ってきた』と感じることもあります(笑)。室内留学ですね。私の場合は、ひきこもりを極めることが逆に社会参加になっている。賃金労働ではないし、社会に認められる働きではないかもしれませんが、これも働いているうちなのでは?という感覚はあります」
それでも無職、ひきこもり、生活保護という表面的なことだけで自分のすべてを判断されることが多いという。「あなた何してる人?」と人に聞かれるのではないか、後ろ指をさされていないか。特に近所の年配女性は自分の母親とダブって体が硬直するほど怖い。体調が良いときに飲みに行くと、名前も職業も偽る。一歩外に出ると非合法活動をしているような気分だという。
自身の家族とは20年前から顔を合わせていない。40代のひきこもりの息子を殺害した元事務次官の父、熊沢英昭容疑者は何を思っていたのかと繰り返し考えている。
「あの父親はいろんな角度から考えたのだと思います。日本のトップ官僚としてこんなことで練馬区の行政を煩わせてはいけない、家庭内で処理することが一国民としての責任の取り方だと考えたのかもしれない。そうだとしたら『ひきこもりを恥と考える根拠は何ですか?』と聞いてみたい。取り調べが終わったら、ぜひ『ひきこもり親子 公開対論』でその苦悩を語ってもらいたい。それが彼にとって罪を償う一つの方法だと思うんです。そして家族から恥の意識を取り払うことが、日本のひきこもり問題の解決への近道なのではないかと考えています」
親子が家族が本音で向き合い、お互いを知る場をつくる。お金にならない“仕事”を背負いながら、池井多さんは今日もひきこもっている。
引用先:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190624-00000092-sasahi-peo
解決サポート
〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL:03-6228-2767